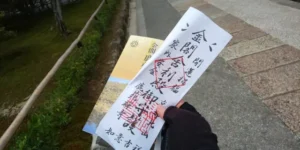金閣寺の黄金の輝きは、訪れる人々をいつ見ても圧倒します。
しかし、その金箔は永遠に貼られたままではありません。
実際には、再建や大改修を経て何度も張り替えられ、そのたびに職人たちの高度な技術と膨大な費用が注ぎ込まれてきました。
さらに現在も、柳生健智氏が日々の点検を行い、傷みや汚れがあれば即座に対応することで、この輝きが守られています。
この記事では、金閣寺の金箔張り替えの歴史、費用、そして現在のメンテナンス体制まで詳しく解説します。
金閣寺の金箔の張り替えは難問続出?

1950年の全焼と1955年の再建
1950年(昭和25年)、金閣寺は全焼という大きな災害に見舞われます。
再建はすぐに計画され、1955年(昭和30年)には再び黄金の舎利殿が姿を現しました。
この時、約2㎏の金箔が使用され、金色の輝きがよみがえります。
初期の金箔がわずか10年で劣化
しかし、この再建時に貼られた金箔は、わずか10年ほどでボロボロに剥がれ始めます。
原因は金箔が極めて薄く、紫外線によってピンホール(小さな穴)ができ、そこから下地の漆が劣化して白化してしまったことでした。
漆は紫外線に弱く、この弱点が大きな課題となります。
分厚い金箔と強力な漆の必要性
この経験から「より耐久性の高い張り替え」が求められるようになります。
従来は金箔の厚みは1万分の1ミリが常識でしたが、研究の結果、義満時代はもっと分厚い金箔を使っていた可能性が浮上します。
そこで、次回の改修ではより厚い金箔が検討されます。
しかし、厚い金箔を貼るには、それに耐えられる強力な漆が必要となりました。
幻の漆「浄法寺漆」との出会い
強力な漆を求めて全国を探した結果、岩手県に江戸時代から続く漆職人が作る「浄法寺漆」が見つかります。
この漆は接着力に優れ、厚い金箔でも剥がれない強度を持っていました。
これが後の大改修の成功に大きく貢献することになります。
1987年・昭和の大改修と職人たちの技
1987年(昭和62年)、昭和の大改修と呼ばれる大規模工事が開始され、1年8か月をかけて金箔の全面張り替えが行われます。
作業には金沢の金箔押師や、木曽平沢の漆職人ら高度な技術を持つ職人たちが参加しました。
一時は不可能とも言われた張り替えでしたが、スペシャリストたちの力で義満建立当時の輝きが見事によみがえったのです。
金閣寺の金箔の張り替えはいつ行われた?

いつ見ても、金ピカで目を奪われる金閣(舎利殿)ですが、1986年の昭和の大改修のときに大々的に張り替えられました。
また、2003年に全面改修されているのですが、このときも傷んでいる部分を含め、一部張り替え作業が行われたそうです。
それから、この金閣寺の輝きが保たれているのは、実は毎日点検されている人物がいらっしゃるとか!
金箔押師の柳生健智さんという方で、開門の9時までに金泊の汚れや埃の付着、傷などがないかの点検をされているそうです。
こんなところで、毎日しっかりとメンテナンスが行われていたのですね。
見えないところで、こんな働きがあったのかと思うと「ありがとう」の言葉しかありません。
柳生健智氏とは?金閣寺の黄金を守る金箔職人
柳生健智(やぎゅう けんち)氏は、金沢を拠点とする熟練の金箔押師で、長年にわたり金閣寺の金箔維持を支えてきた第一人者です。
金閣寺の開門前、毎朝9時までに舎利殿の外観を点検し、埃や汚れ、剥がれの兆候がないか細かく確認します。
大きな傷みがあれば修復作業を行い、必要があれば部分的な金箔補修も担当します。
まさに、金閣寺の輝きの「現在の守り手」として欠かせない存在です。
全面張り替えと部分張り替えの違い
金閣寺の金箔張り替えは、大規模改修と小規模補修で方法が異なります。
1987年の昭和大改修のような大規模工事では、見た目や耐久性を統一するため全面張り替えが行われました。
一方、2003年のような部分補修では、日光や風雨にさらされて劣化が進んだ部分だけを張り替え、比較的状態が良い部分はそのまま維持されました。
毎日の点検で劣化部分を早期に発見することで、全体の張り替えサイクルを延ばす工夫がされています。
金閣寺の張り替える「金箔」と「漆」はどこから仕入れる?
金閣寺の張り替えに使われる金箔や漆は、一般市場では入手できない特別な仕様です。
金箔は石川県金沢市の金箔職人から供給されます。
金沢は国内生産の約98%を占める産地で、文化財修復の経験を持つ認定職人が特注で制作します。
昭和の大改修でも、耐久性を重視した厚みのある金箔が作られました。
漆は岩手県二戸市(旧・浄法寺町)の「浄法寺漆」が使用されます。
接着力と耐久性が極めて高く、文化財修復において標準的に採用されています。
流通量が少なく、文化財向けに優先的に確保されるため、入手は文化庁や寺院を通じた専用ルートとなります。
つまり、金箔も漆も一般販売ではなく、文化財修復専門の職人ネットワークと契約する形で調達されるのです。
金箔の張り替えに必要な金は延べ棒なら何本分?
金の延べ棒20本

1987年の昭和大改修では、金閣寺の全面張り替えに約20kgの金箔が使用されました。
これを金の延べ棒で換算するとおよそ20本分です。
- 当時(1987年)の金相場:約3,000万円相当
- 現在(2025年換算):約2億円相当
つまり、金閣寺の金箔張り替えは、現代の価格で考えれば延べ棒20本=約2億円というスケールの大工事。
金の相場が上昇した今、次回の全面張り替えはさらに大規模な費用になることが予想されます。
材料費より高額な人件費と技術料
金箔張り替えの費用は材料費が注目されがちですが、実際には人件費と技術料が大きな割合を占めます。
熟練の金箔職人や漆職人は国内でも限られた存在で、長期間にわたる工事期間中ずっと作業が続くため、人件費は数千万円単位になることもあります。
また、文化財修復のため足場や保護設備、検査費用などの管理コストも加わり、最終的な総工費は材料費の2倍以上に膨らむことも珍しくありません。
金閣寺の金箔の定期メンテナンスと次回張り替え予測

金箔張り替えは誰が決めて費用は誰が負担する?
金閣寺の金箔張り替えは、運営主体である臨済宗相国寺派(鹿苑寺)が判断します。
京都市や京都府が直接決定するわけではありませんが、国の特別史跡・特別名勝かつ世界遺産であるため、文化庁や京都府教育委員会の文化財保護部門と調整を行い、修理計画が承認されます。
費用は、寺院の自己資金、国や京都府・京都市の補助金、そして企業や個人からの寄付金を組み合わせて賄われます。
昭和の大改修(1987年)の際も、国や自治体の補助金と寄付が大きな財源となりました。
大規模工事は数億円単位の費用が必要なため、社会全体で支える形が取られています。
次回張替えは2030-2040年頃
金閣寺は、2003年の部分補修以降、大規模な金箔張り替えは行われていませんが、柳生健智氏らによる日常点検で美しさが維持されています。
通常、金箔の全面改修は数十年おきに実施される傾向があり、過去の例からみても次の本格的な張り替えは2030年前後〜2040年頃と予想されています。
とはいえ、近年は金箔の品質や漆の耐久性が向上しているため、適切なメンテナンスが続けば、その時期がさらに延びる可能性もあります。
後継体制と今後の展望
現在ご本人が第一線で活躍する一方、ご自身の息子らを含む4名体制で金箔維持にあたっており、後継者育成も進んでいます。
技術継承と信頼性の確保を重視し、若手には厳選された人物のみを採用し、責任感を持って取り組んでおられます。
将来的には彼らの活躍により、主導権が移る可能性もありますが、現時点では柳生健智氏本人が金閣寺の「黄金の守り手」として大きな役割を担い続けているのです。
金閣寺の張り替えの値段はおいくら?何回張り替えられたの?

1950年に再建されたときの金の原価だけでも、おおよそ1170万円の費用が掛かったそうです。
1986年〜1987年の大改修のときは、当時の金の原価だけで2億6860万円の費用がかかったそうですが、実際は厚さ5㎜の金(20㎏)が必要なことから、値段も一気に飛び跳ねたことになります。
ちなみに、義満の頃は現代のお金に換算すると、数百億円の費用が掛かったそうです。
張り替えの回数も、1955年の再建から2003年の全面改修の一部張り替えを合わせると3回行われていることになりますが、全面的にみると2回の張り替え作業が行われたことになります。
金閣寺の貼り換えはいつ?【まとめ】
金閣寺の金箔張り替えは、1955年再建時、1987年昭和大改修、2003年部分補修と、大規模な工程を経て現在の姿を保っています。
そしてその美しさを日々守っているのが、柳生健智氏による毎朝の点検作業です。
張り替えのタイミングは数十年に一度ですが、日常的なメンテナンスがあるからこそ、訪れる誰もが黄金の輝きを堪能できるのです。