織田信長が行った「比叡山延暦寺の焼き討ち」は、日本史の中でも特に残虐な出来事として知られています。
多くの僧侶や民衆が犠牲となったとされるこの事件ですが、なぜ仏教の総本山とも言える延暦寺が標的になったのでしょうか?
今回は、その背景や信長の狙い、明智光秀の関与、新たな研究で見えてきた真実までをわかりやすく解説します。
比叡山延暦寺の関連記事一覧
比叡山延暦寺の焼き討ちの理由とは?
延暦寺とはどのようなお寺?

滋賀県と京都府の県境にある比叡山延暦寺は延暦23年(804年)に唐へと渡り、帰国した最澄が開いた天台宗のお寺です。
禅、天台宗教学、密教などを学んだ最澄が開いた延暦寺は、仏教を学ぶことのできる学校のような役割を果たしていました。
そのためここから多くの有名な僧が輩出されることとなり、延暦寺は仏教の母山と呼ばれるようになります。
今でこそ、お寺で修行する僧は武器を持たず、打ち壊しなど武装するイメージはありません。
しかし、昔の寺は武器を持ち戦う僧兵を持っていました。
武装した僧たちは僧兵と呼ばれ、延暦寺もまた強力な僧兵を抱えていました。
延暦寺の僧が武装化した理由
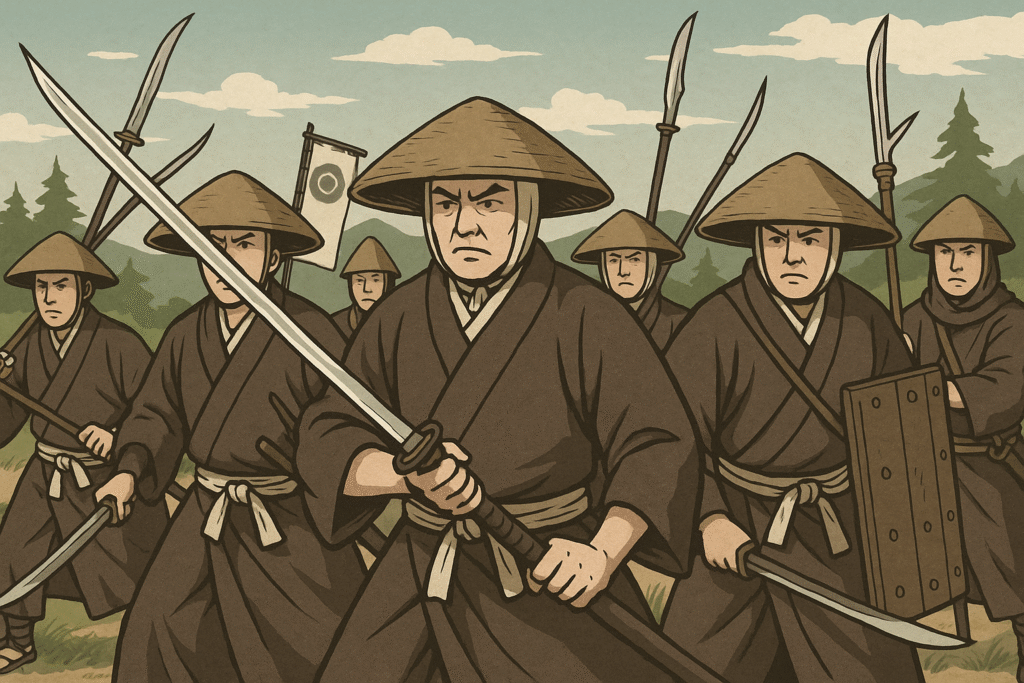
最澄が延暦寺を開いてから多くの僧を輩出しましたが中でも、円仁と円珍と呼ばれる僧は唐へと渡り、修行を重ねたくさんの仏典を日本へと持ち帰りました。
これは日本の仏教に大きく貢献することとなります。
しかし、その後の正暦4年(993年)頃から延暦寺の僧の中で円仁派と円珍派が対立するようになり、ついに円仁派が円珍派の拠点を打ち壊すまでの対立となりました。
円珍派の僧たちはその後、比叡山を下り三井寺へと移り延暦寺から独立することとなります。
このような派閥争いの中で、武装する僧たちが増え、延暦寺の武力は年々、強いものとなっていきました。
武力を持った延暦寺は権力を持つようになり平安時代、強い権力を持っていた白河天皇でさえ延暦寺を危険視するようになります。
天皇や朝廷、武家でさえも延暦寺を恐れるようになったのです。
延暦寺と織田信長は対立関係に
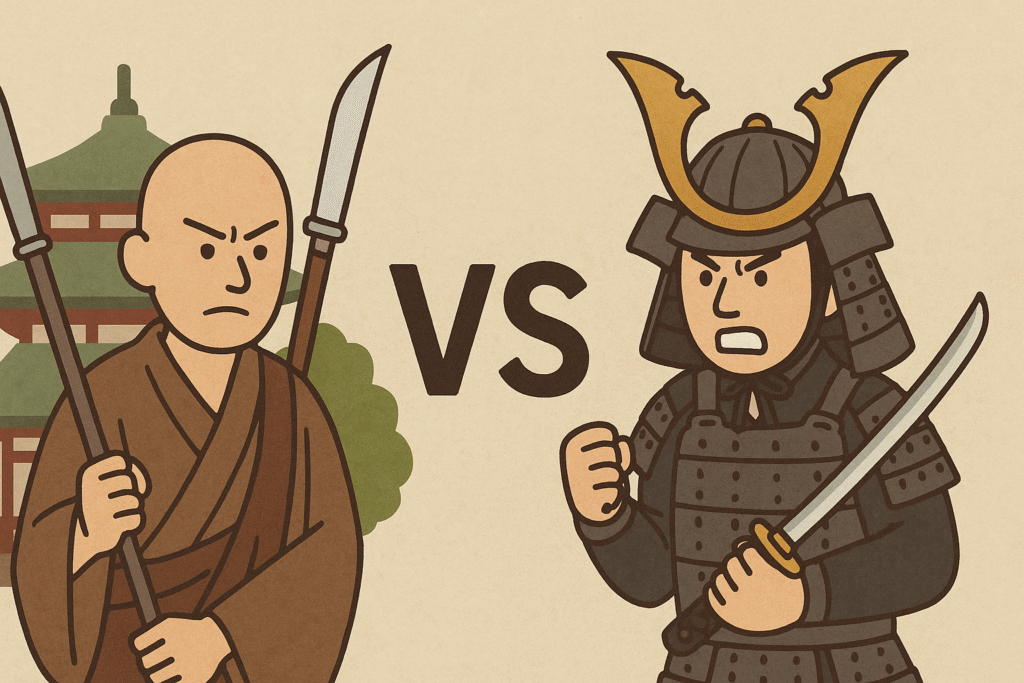
強大な武力と権力そして財力を持っていた延暦寺は戦国時代にはいっても恐れられる存在のままでした。
戦国時代、日本の統一を目指していた織田信長にとっても延暦寺は扱いにくい存在であったのではないでしょうか。
織田信長は、延暦寺の勢力を落とすため延暦寺の寺領を奪います。
これに対し延暦寺は朝廷に働きかけ、朝廷から織田信長に対し寺領を返還するよう求めます。
しかし、朝廷から返還するよう要求されても織田信長は従うことはありませんでした。
当時、織田信長は将軍・足利義昭のもとで日本の統一を目指しており、朝廷と強い関係を持った織田信長に従う大名たちは多くいました。
上洛していた織田信長は全国の大名に上洛を要求します。多くの大名がその要求に従いましたが、越前国の朝倉義景だけは上洛を拒否。
これに起こった織田信長はすぐさま朝倉義景の討伐に乗り出すのでした。
元亀元年(1570年)、織田信長は朝倉義景を倒すため越後国を攻撃、しかし、織田信長の妹の嫁ぎ先であった浅井長政が寝返り、織田軍は一時撤退を余儀なくされました。
織田信長が一時撤退したことにより朝倉・浅井連合軍の勝利に見えましたが、戦いは一転し織田軍の勝利に終わります。この戦いは姉川の戦いとして知られています。
朝倉・浅井軍の兵を匿った延暦寺
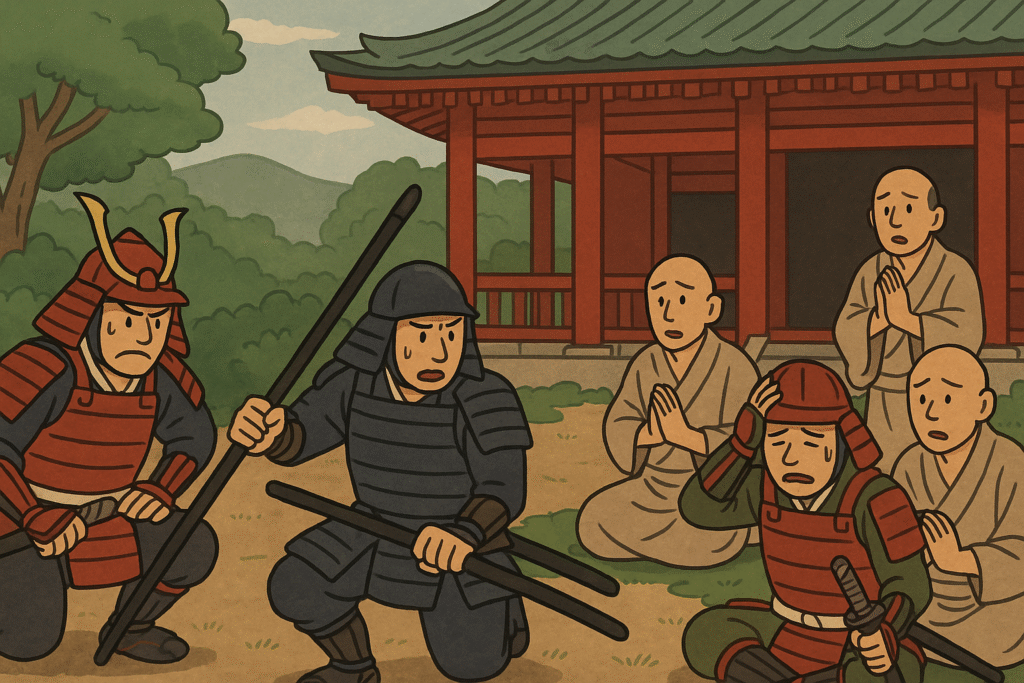
姉川の戦いで敗れた朝倉・浅井軍の一部の兵たちは延暦寺へと逃れたとされ、延暦寺は多くの兵を匿うこととなりました。
当時から恐れられていた織田信長ですので、ここですぐ敵の兵を匿っている延暦寺を焼き払うのかと思いますが、織田信長は意外にも平和的に話で解決しようと乗り出します。
織田信長は「織田軍の味方をすれば、以前取り上げた寺領は返す。」と延暦寺に要求します。
つまり延暦寺は朝倉・浅井軍の兵を追い出せば、以前に奪われた寺領が戻ってくるということです。
しかし、延暦寺は織田信長の要求を拒否、依然朝倉・浅井軍の兵を匿い続けたのです。
これに対し織田信長は激怒。織田信長は完全に延暦寺を潰そうと考えたのです。
延暦寺を焼き討ちに

こうして元亀2年(1571年)、敵となった延暦寺の無力化を図った織田信長は全軍に延暦寺への攻撃を命じました。
仏教の母山である延暦寺に火を放った織田信長。
『信長公記』によると比叡山のほとんどが燃えたとされ、また僧や女子供関係なく多くの人を殺害したとされています。
記録によると3000人から4000人が殺害されたとされ、仏のもとで修行をする僧を殺害し延暦寺に火を放つなど仏教を敵にしたとも言えるこの大事件から織田信長の残虐性が見られます。
延暦寺から少し離れた坂本、堅田周辺にも火を放ったとされ延暦寺のみならず、僧たちが逃げ込んだ日吉大社も焼き払ったとされています。
織田信長の焼き討ちに反対していた武将はいたのか?

延暦寺焼き討ちは、織田信長の命令で強行されたものですが、その決定に対して家臣たち全員が賛同していたわけではなかったと考えられています。
たとえば、信長に仕えていた滝川一益(たきがわ かずます)や丹羽長秀(にわ ながひで)らは、信長に忠実だったものの、仏教勢力への攻撃には一定の躊躇いを見せたとされる記録もあります。
また、柴田勝家のような古参の家臣の中には、信長の過激な手法に対して内心では不満を持っていた者もいたと推測されます。
ただし、当時の信長の軍は「中央集権体制」の構築中であり、家臣たちが表立って反論することは難しい空気だったともいえます。
信長の命令は絶対であり、「仏敵」として恐れられる存在に抗えば、即座に粛清される可能性もあったのです。
明智光秀のように積極的に加担した者もいれば、内心では複雑な思いを抱えながらも従わざるを得なかった武将もいた――延暦寺焼き討ちは、戦国時代という時代背景の中で、多くの武将たちが葛藤した決断の一つでもあったのかもしれません。
『信長公記』は誇張して記録されている?延暦寺焼き討ちの事実
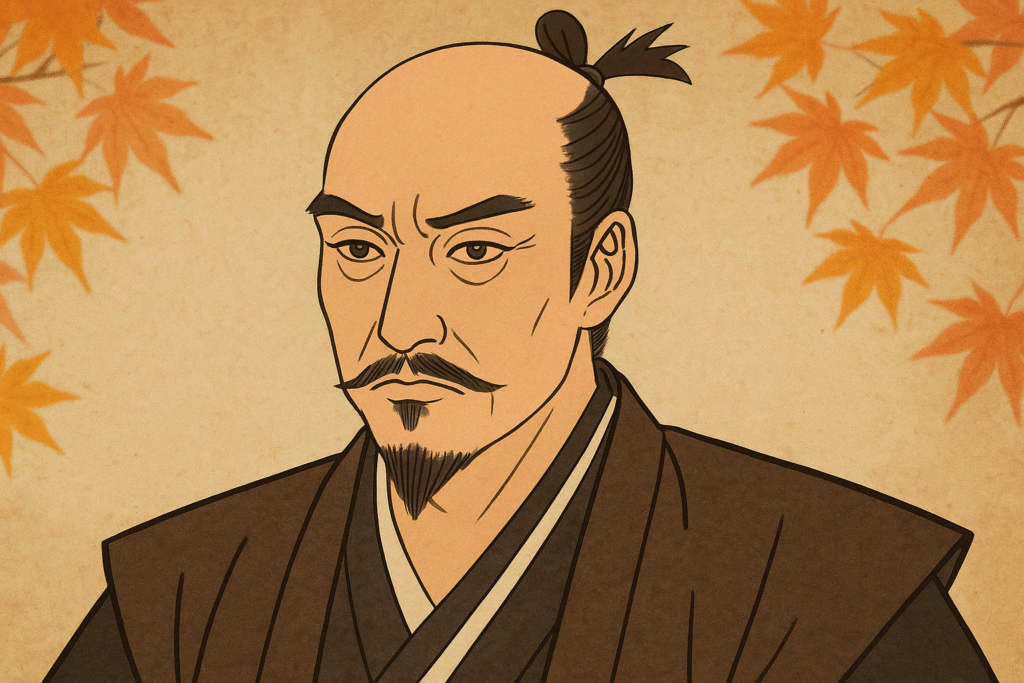
延暦寺に火を放ち多くの人々を殺害したとされる織田信長。
この延暦寺焼き討ちによって多くのお堂が燃やされたと考えられていました。
しかし、近年の研究では実は根本中堂と大講堂と呼ばれるお堂だけの被害で済んでいたのではないかと指摘されています。
1981年、考古学者の兼康保明によって記された「織田信長比叡山焼打ちの考古学的再検討」には、延暦寺焼き討ちの被害は根本中堂、大講堂のみで、その他のお堂は焼き討ちされる以前に廃絶していたと記されています。
また『言継卿記』などに3000人の僧たちが一人一人斬首されたと記されるも、当時、延暦寺の多くの僧が山を下りて延暦寺に近い坂本周辺に住んでいたということから、3000人もの大量虐殺が行われたというのは誇張表現ではないかと考えられています。
これらの説は事実かどうか分かりませんが、もし織田信長の大量虐殺は誇張された話であったのなら、残虐的な性格であったとされる織田信長の人物像も少し変わってくるのではないでしょうか。
明智光秀の功績
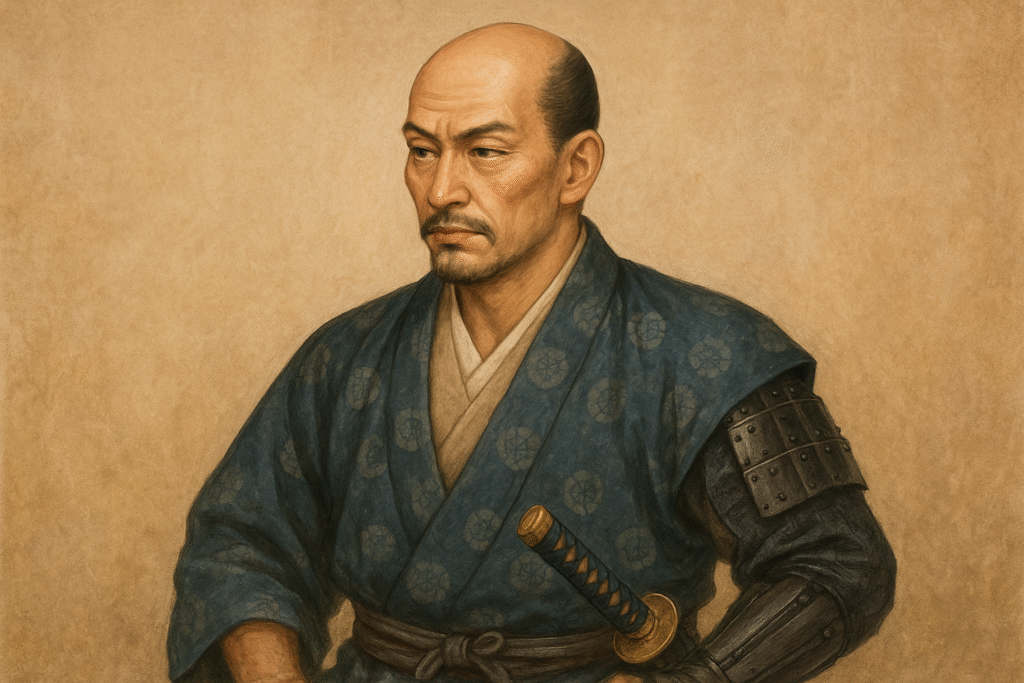
明智光秀
のちに織田信長を裏切る明智光秀は延暦寺焼き討ちで功績を残しています。
延暦寺の焼き討ちの計画を教えられた家臣の明智光秀は、すぐさま琵琶湖西部で大きな勢力であった和田氏や八木氏に援軍を頼んだとされています。
和田氏に送った「仰木攻めなで切り」と呼ばれる書状には予想される戦地や、敵を見かけたら皆殺しにするように。
と記されており、延暦寺の焼き討ちに積極的に参加していたことが分かります。
武功を挙げた明智光秀は戦後、織田信長に評価され近江国の志賀群を与えられることとなりました。
間もなくして後に明智光秀の居城となる坂本城が築城されたのでした。
延暦寺焼き討ちはなぜ行われた?明智光秀の功績もわかりやすく解説!【まとめ】
比叡山延暦寺焼き討ちは、信長の冷酷な一面を象徴する事件として知られていますが、近年では被害の規模や信長の動機に再検証が進んでいます。
信長の残虐性ばかりが注目されがちですが、戦国時代の権力闘争や仏教勢力との対立という背景を知ることで、より深い理解が得られるのではないでしょうか。




