大阪城と言えば豊臣秀吉を思い浮かべる人が多いですが、実際には何度も再建され、現在見られる天守閣は3代目であることをご存知でしょうか。
この記事では、大阪城がいつ誰によって建てられたのか、そして何のために築城されたのかを詳しく解説していきます。
大阪城はいつ建てられたの?誰が建てたの?
現在見られる大阪城は、1931年(昭和6年)に復興されました。
この敷地には当初、石山本願寺がありました。
城内の修道館近くに石山本願寺跡がありますので、大阪城に行った際には見て下さいね。

石山合戦の末、織田信長が敷地を手に入れる

石山本願寺は、お寺自体も、僧侶たちもとても強大で武装勢力もありました。
お城の石垣というのは、元々は寺院が土留めのために、石を積み重ねていたものが発展したと考えられています。
石山本願寺と織田信長は、1570年(元亀元年)から1580年(天正8年)にかけて10年にも及ぶ石山合戦を繰り広げていましたが、最後は信長がこの敷地を手に入れました。
しかし、1582年(天正10年)に本能寺の変で信長は死んでしまいます。
豊臣秀吉が初代の大阪城を築城
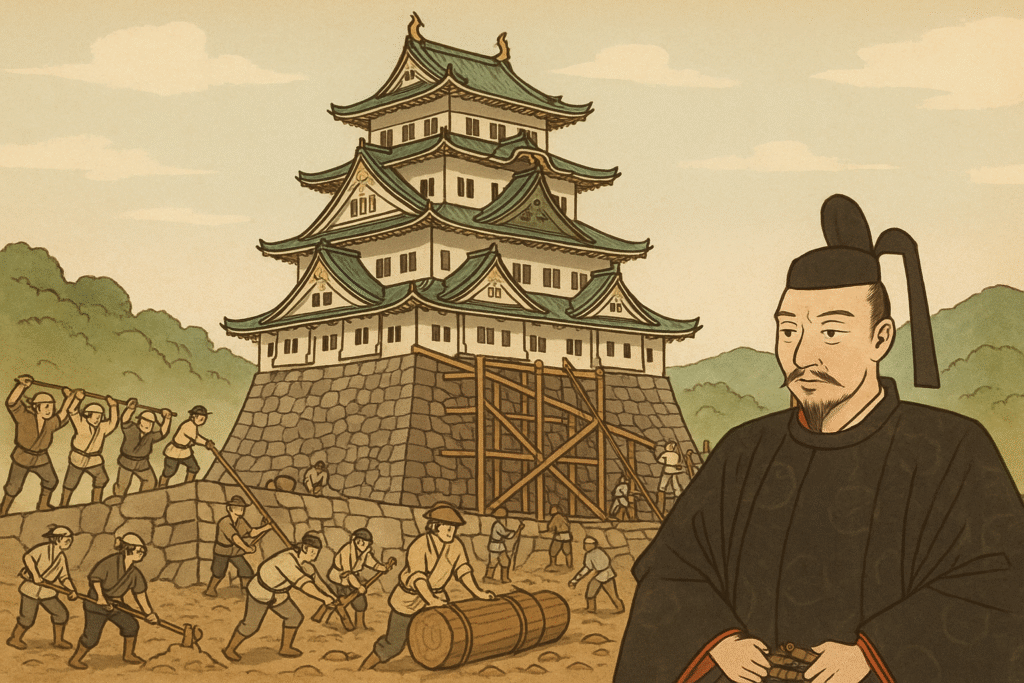
その後、豊臣秀吉が天下人となり、1583年(天正11年)石山本願寺の地に大阪城を築城を開始しました。
秀吉は、信長の遺志を受け継いだのかも知れませんね。
また、大阪は瀬戸内海の海路を利用して経済の発展に繋がる好立地だったことが信長の狙いとも言われています。
秀吉の大阪城は、初代天守閣、石垣、本丸、二の丸など1588年(天正16年)にほぼ完成します。
しかし、1598年(慶長3年)に秀吉は死んでしまい、大坂城は1615年(慶長20年)に大坂夏の陣で天守閣は焼失してしまいます。
徳川秀忠が2代目の大阪城を再築
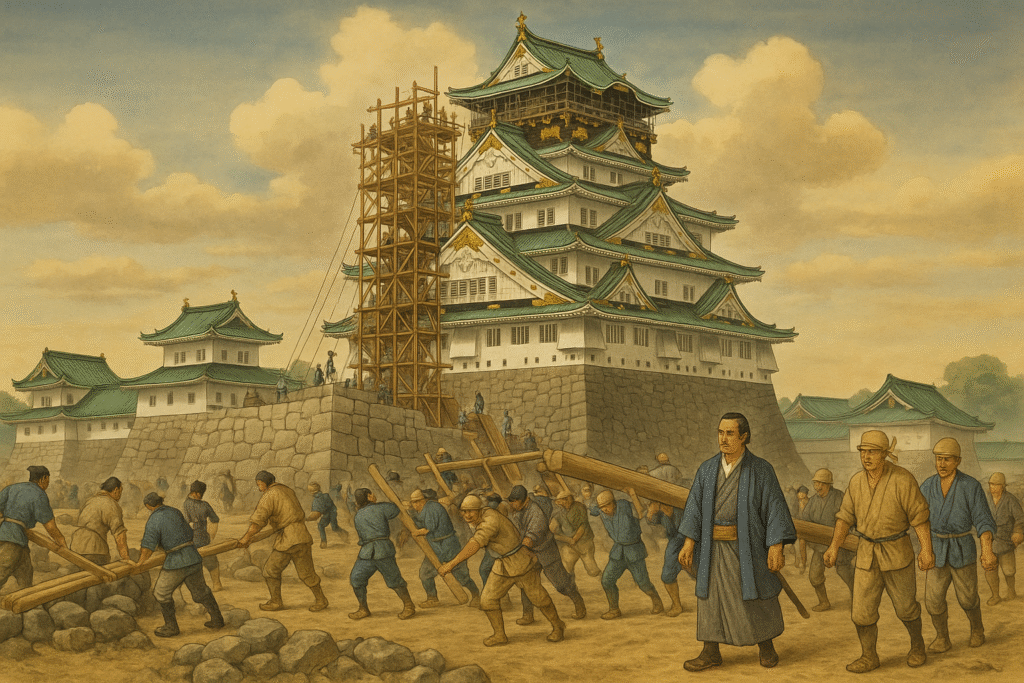
徳川幕府2代将軍・秀忠は、1620年(元和6年)に大坂城を再築しました。
秀吉の時代のものと比べると、敷地は狭くなりましたが、天守の高さは58メートルと高くなり徳川の威光を示しています。
2代目天守閣ですが、1865年(寛永5年)落雷のため、焼失してしまいます。
それから1931年(昭和6年)の3代目復興まで、天守閣のない大坂城となっていました。
大阪市によって3代目が復興

3代目の天守閣は、大阪市民の熱意によって約750億円ほどかけて、復興されました。
これが、現在見られる大阪城の天守閣です。
鉄筋コンクリート製なので、昭和20年の第二次世界大戦の空襲にも耐えたのだ、と思われます。
自分が以前大坂城をブラブラ歩いてたら、多分地元のおじさんが寄ってきて「石垣のここの穴は米軍が撃った銃弾の跡なんだ」と説明をしてくれました。
それ以来、大坂城に行く度にその話しを思い出しています。
今度会ったら、大阪城について何のために建てたのかとか、いつ建てられのかも聞いてみようかなあと思います。
大阪城の歴代天守閣の特徴比較

現在の大阪城天守閣は3代目ですが、これまでどのような天守閣が建てられてきたのかを表でまとめました。
| 天守閣 | 築城者 | 築城年 | 高さ | 構造 / 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 豊臣秀吉 | 1583年(天正11年)~1585年頃 | 約40m | 木造 / 天下統一の拠点として築城。1598年秀吉死去、1615年大坂夏の陣で焼失。 |
| 2代目 | 徳川秀忠 | 1620年(元和6年)~1629年頃 | 約58m | 木造 / 徳川幕府が再築。1868年(明治元年)落雷で焼失。 |
| 3代目 | 大阪市(市民募金) | 1931年(昭和6年) | 約55m | 鉄筋コンクリート造 / 大阪市民の寄付により再建。昭和の戦火も耐え抜き現存。 |
※高さは推定値。石垣含む天守閣全体の高さです。
豊臣秀吉の初代天守閣は政治と軍事の拠点として、徳川幕府の2代目天守閣は江戸幕府の権威を示す象徴として、そして現在の3代目は市民のシンボルとして、それぞれ時代の目的と背景を持って築かれてきたことがわかります。
大坂城は何のために建てられた?

大阪城が建てられた3つの目的
権力誇示
大阪城は、豊臣秀吉が天下統一を果たした後、その権力を全国に示すために築かれました。
当時の秀吉は、日本一高く大きな天守閣を持つ城を建てることで、自分こそが天下人であると誇示しようと考えていたのです。
しかし大阪城の役割は、単なる権力誇示だけではありませんでした。
軍事拠点
まず、軍事拠点としての役割があります。
大阪城は難攻不落の堅城として築かれ、有事の際には籠城して指揮を執るための重要な要塞でもありました。
政治・経済の拠点
また、大阪は瀬戸内海や京都への交通の要所に位置し、経済や物流の中心でもあったため、政治・経済拠点としての機能も大きかったと言えます。
秀吉は大阪城を築くことで、軍事と経済の両面から日本統治を盤石なものにしたかったのでしょう。
築城には多くの諸大名や職人たちが動員され、作業人数は多い日で1日3万人にも及んだと伝わっています。
5年ほどで完成しましたが、それだけの短期間で築城できたのは、昼夜問わず作業が行われたからでしょう。
筆者の感想
先日、名古屋城の石垣復旧説明会に参加した際、石垣を人力だけで組み立てる実演を見ましたが、重機やクレーンもない時代にあれほど大きな石垣や天守閣を作り上げた秀吉の権力と統率力には改めて驚かされます。
まさに、城の大きさがそのまま築城主の権力と影響力を示していた時代だったと言えるでしょう。
明治時代になると、大阪城内の多くの建築物は取り壊され、敷地は陸軍の施設として利用されるようになりました。
そして現在は、史跡公園として整備され、市民や観光客の憩いの場となっています。
大阪城はいつ建てられた?誰が何のために建てたのか検証します!【まとめ】
今回は、大阪城はいつ建てられたのか、何のために建てられたのかについて検証しました。
大阪城は、国内だけでなく、海外からも多くの観光客が訪れる人気のスポットとなっています。
多門櫓、千貫櫓、焔硝蔵などの重要文化財も見応えがあり、城内はボランティアガイドさんもいるので、質問には気さくに答えてくれ疑問が解決しますよ。
現在、大坂城豊臣石垣公開プロジェクトがあり、地下に埋もれた秀吉時代の石垣を掘り起こす活動が行われています。この石垣が見られること頃には、4代目の天守閣になっているかもしれませんね。







