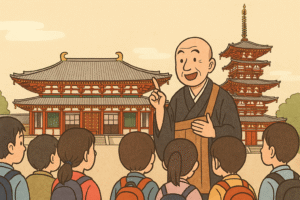薬師寺といえば、美しい三重塔や色鮮やかな伽藍が印象的なお寺ですが、その歴史は1300年にも及びます。
では、この壮大な薬師寺を一体「誰が」「何のために」建てたのでしょうか?
本記事では、薬師寺創建のきっかけとなった天武天皇と持統天皇の関係、建立の目的、そして薬師寺が現代までどのように受け継がれてきたのかを、わかりやすく解説していきます。
薬師寺は誰が建てた?
天武天皇が薬師寺の建立を発願した理由
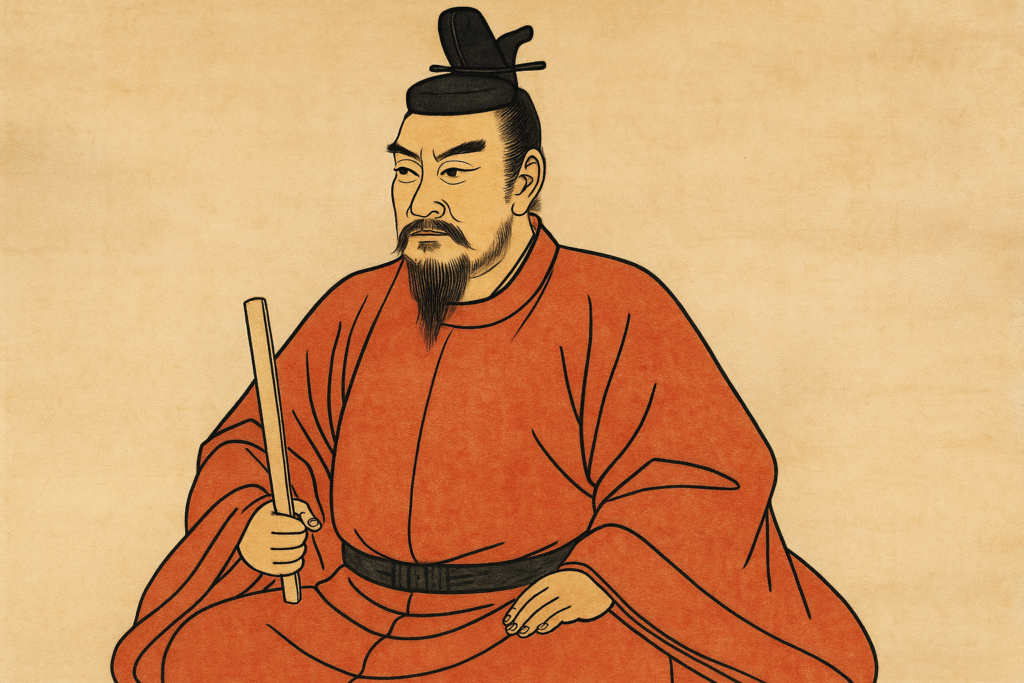
天武天皇
薬師寺は、680年に天武天皇が皇后・鸕野讃良皇女(うののさららのひめみこ/のちの持統天皇)の病気平癒を願って発願したことに始まります。
建設が進められましたが、天武天皇は完成を見ることなく崩御してしまいます。
その後、天武天皇の意思を引き継いだ持統天皇が建立を継続し、薬師寺は完成へと至りました。
天武天皇とはどんな人物だったのか?
天武天皇は飛鳥時代の第40代天皇であり、「壬申の乱(じんしんのらん)」に勝利したことで歴史に名を残す人物です。
後世には「神」として崇められることもありました。
壬申の乱の背景と天武天皇の即位
天武天皇(当時は大海人皇子)は、兄である天智天皇から次期天皇に推されていましたが、天智天皇は最終的に自分の息子・大友皇子(後の弘文天皇)を後継者に指名します。
これを快く思わなかった大海人皇子は、出家を理由に吉野へ身を引きますが、内心では「天皇の座は譲れない」と強い思いを抱いていたのです。
やがて大友皇子が即位して弘文天皇の時代が始まると、大海人皇子は挙兵。ここに壬申の乱が勃発します。
結果、大海人皇子が勝利し、弘文天皇は自害。
天武天皇として即位を果たしました。
藤原京の整備と薬師寺の創建
即位後、天武天皇は新たな都「飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)」を造営し、中央集権国家としての体制づくりを進めます。
その一環として、都を藤原京に整備。
そしてこの藤原京にて、皇后の病気平癒を願って薬師寺の建立を発願することになります。
薬師寺はのちに平城京へと移転される
創建当初の薬師寺は、現在の奈良県橿原市にあたる藤原京に建立された本薬師寺が原型です。
しかし、710年に都が平城京へ遷都されると、薬師寺も現在の場所へと移転されました。
このとき、すでに即位していた持統天皇が薬師寺移転を主導したとされています。
藤原京に建てられた「本薬師寺」とは?
薬師寺と聞くと現在の奈良・西ノ京にある美しい伽藍を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は創建当初の薬師寺は現在の場所ではなく、藤原京(現在の奈良県橿原市)に建てられていました。
この創建時の薬師寺は「本薬師寺(もとやくしじ)」とも呼ばれています。
本薬師寺は、天武天皇が皇后・鸕野讃良皇女(後の持統天皇)の病気平癒を願って、飛鳥時代の680年に建立を発願したもので、日本最初の本格的な国家仏教寺院とも言われます。
しかしながら、その後710年に都が平城京に移されると、薬師寺もそれに伴って現在の奈良市西ノ京へと移転されました。これにより、藤原京にあった本薬師寺は徐々に衰退し、次第に廃寺となっていきます。
現在の本薬師寺跡地には、当時の礎石や遺構が発掘されており、史跡として整備されています。
特に初夏から夏にかけては、薬師寺にちなんで植えられたホテイアオイの花が一面に咲き誇り、多くの観光客や写真愛好家が訪れる名所にもなっています。
つまり、薬師寺は天武天皇と持統天皇の時代に藤原京で誕生し、その後平城京への遷都にあわせて移転した、都とともに歩んできたお寺なのです。
天武天皇は薬師寺の完成を見ることもなく崩御されますが、その意思を引き継ぎ薬師寺の完成を見届けたのが、持統天皇だったのです。
持統天皇はどんな人なのか?
持統天皇は女性。
当時は天皇が政治を司っていたので、今でいう女性政治家というほうが分かりやすいかも知れません。
持統天皇は、律令を制定、戸籍の整備、本格的な都造営など、今日の日本の礎を築いた人なのです。
律令とは、皆さんも歴史で習った「大宝律令」のことで、刑罰などの規定や政治の組織や税金、労役などの規定を本格的に取りまとめました。
女性進出の動向は1300年前からあったのですね。
女性が栄えると、その国は更に栄えるなどといわれますが、一理当たっているのかも知れません。
現在の政治も、もっと女性の起用があってもいいと思いませんか?
薬師寺は誰が建てたのかについては、天武天皇が発願し薬師寺は建立されますが完成する前に崩御され、持統天皇が意思を引き継ぎ完成へと導きます。
つまり薬師寺は誰が建てたかは。天武天皇と持統天皇にが建てたことになりますが、皆さんはどのように思われますか?
檀家を持たない大寺院として「再建」を行った
古代に建てられた薬師寺から現代の薬師寺は、再建や復興遂げてきた歴史のある奈良を代表するお寺です。
薬師寺はなんのために建てたかは、やはり古代の白鷗文化や現代に至るまでの薬師寺の歴史を絶やすことなく継承していくことにあると思います。
昭和に入り、建物の倒壊などで寂しい状況の中にあった薬師寺は、高田好胤というお坊さんにより見事復興を遂げ、金堂をはじめ西塔が再建されるなど、美しい薬師寺の姿が再び誕生しました。
創建当初に近い建物として再建された薬師寺は、とても貴重なお寺のひとつです。
薬師寺は誰が建てた?【まとめ】
薬師寺は、天武天皇が皇后の病気平癒を願って発願し、亡き後その意思を受け継いだ持統天皇によって完成されたお寺です。
その背景には夫婦の強い絆と人々の健康を願う深い想いが込められていました。
時代を越えて再建と復興を遂げてきた薬師寺は、今もなお多くの人々に愛される奈良の名刹としてその歴史を刻み続けています。