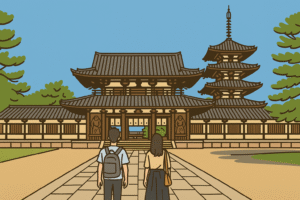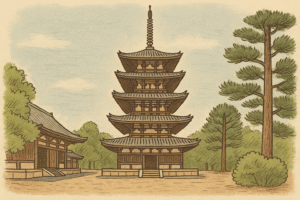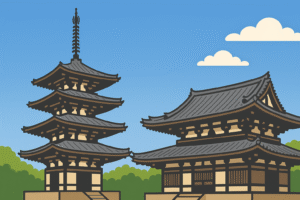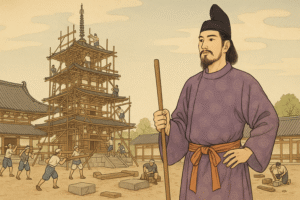法隆寺には数多くの貴重な仏像が安置されていますが、なかでも注目されるのが秘仏「救世観音(くぜかんのん)」です。
この観音像は、聖徳太子の等身大と伝わる貴重な仏像で、通常は拝観できない完全秘仏として長年守られてきました。
しかし春と秋の特別開扉の期間だけは、実際にその姿を見ることができます。
この記事では、救世観音の公開時期、安置場所、混雑を避けるポイント、さらには噂される「怖い話」まで、わかりやすく解説します。
法隆寺の関連記事一覧
法隆寺の救世観音とは?名前・造り・由来を紹介
【奈良・法隆寺/観音菩薩立像(救世観音)(飛鳥)】観音が普通持つことは無い舎利壺を持つ。止利様式の特徴を踏襲し、北魏的な仏面。光背が後頭部に打ち付けられている。生身の人間のような風貌は高村光太郎が評したように妖気すら感じさせる。 pic.twitter.com/C47DZ3jUZo
— 美しい日本の仏像 (@j_butsuzo) January 11, 2025
法隆寺の救世観音(くぜかんのん/くせかんのん)は、一般的には「くぜかんのん」と呼ばれることが多い観音像です。
像はクスノキ製の一本造りで、漆箔(しっぱく)造りという技法で金箔が施されています。
高さは178.8cmあり、聖徳太子の等身大と伝えられています。
飛鳥時代の平均身長からすれば、かなり大きな像です。
この観音像は739年に造られたとされる秘仏で、長らく誰にも公開されないままでした。
しかし、明治17年(1884年)、アメリカ人美術史家のフェノロサが僧侶たちを説得し、約700年ぶりに御開帳されました。
そのとき、像は約450メートルの布や和紙で丁寧に包まれており、保存状態は極めて良好だったといわれます。
その後、1951年には国宝に指定され、現在も春と秋の特別公開時のみ拝観が可能となっています。
まさに、歴史と謎に包まれた貴重な仏像です。
法隆寺の救世観音の最新の公開日程は?例年の傾向とチェック方法

法隆寺の救世観音は、例年「春」と「秋」の2回、特別開扉(特別公開)として一般に公開されますが、公開日程は毎年微妙に変動します。
例えば、2023年は春が「4月11日〜5月18日」、秋が「10月22日〜11月22日」でしたが、年によっては開始日が前後したり、期間が1〜2日短くなることもあります。
そのため、直近の公開スケジュールを知りたい場合は、以下の方法で最新情報を確認しましょう。
- 法隆寺公式サイト(https://www.horyuji.or.jp/)の「お知らせ」ページをチェック
- 奈良県観光公式サイトなどのイベント情報カレンダーを見る
- 観光ポータル「いこーよ」「じゃらん」「るるぶ」なども参考に
- SNS(X・Instagramなど)で「法隆寺 救世観音 公開」などで検索するのも◎
特に、法隆寺の公式ページでは「特別公開」の情報が1〜2か月前に掲載されるのが通例です。
春なら3月初旬、秋なら9月初旬あたりから情報をチェックしておくと安心です。
なお、混雑を避けたい場合は、公開初日と土日・祝日を外した平日の午前中が狙い目です。
救世観音はどこに安置されているの?
法隆寺大宝蔵院#法隆寺大宝蔵院#奈良まほろばソムリエ検定勉強中 pic.twitter.com/rdulL3pLAs
— 岡田一也 (@chibireolion1) September 15, 2023
法隆寺の救世観音像は、境内東側にある「大宝蔵院(たいほうぞういん)」という収蔵施設の中に安置されています。
この大宝蔵院には、ほかにも百済観音像や夢違観音像、玉虫厨子などの文化財が多数展示されており、いわば法隆寺の“宝物館”ともいえる場所です。
救世観音像は、大宝蔵院の中の「救世観音像安置厨子(ずし)*という専用の厨子に納められており、普段は扉が閉ざされていて、その姿を見ることはできません。
特別公開は他の仏像も対象なの?
春や秋の「特別公開」とは、救世観音だけではなく他の仏像も一挙に公開されるのか?と思う方もいるかもしれませんが──
答えは、いいえ、特別公開の対象は救世観音像のみです。
他の仏像たち──百済観音像や夢違観音像などは、常設展示の対象として通常時から拝観可能です。

つまり、特別公開のタイミングは救世観音だけの厨子が開かれる“レアイベント”なのです。
とはいえ、同じ大宝蔵院の中で展示されている仏像を一緒に拝観できるため、「救世観音も百済観音も同時に見られる」貴重なタイミングであることに変わりはありません。
なお、展示替えや保存修復によって一部展示が見られないこともあるため、最新の展示状況は法隆寺の公式サイトで事前確認しておくのがおすすめです。
法隆寺の救世観公開のときの混雑予想は?

普段見ることができないので、やはりどんなものか見てみたい‼と思いますよね。
やはりその期間を狙って法隆寺の救世観音を一目ようと訪れる人は多いのではないでしょうか?
また、10月~11月は修学旅行などのシーズンともいえますので、大勢の人に遭遇することになるかもしれません。
法隆寺での修学旅行は、団体で行動するケースも多いので、特別開扉のときにバッティングした場合はかなりの混雑ぶりになるかも知れません。
また、新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことから、本来の賑わいや観光客の数も徐々に戻ってくると予想されます。
特に外国人観光客も更に増えるなど、救世観音の公開を狙って訪れる人もあるかもしれません。
法隆寺の救世観音公開を楽しみにしていたのに、人ごみを見に行ったなどということがないように、時間など早めに行くなど工夫されてみてはいかがでしょうか?
法隆寺の救世観音は怖いの?
「世の苦しみからあらゆる民衆を救済する」という救世観音に、本当は怖い観音様だという容疑がかけられていたことを皆さんはご存じでしたか?
実は…
法隆寺の救世観音は、聖徳太子の呪いがかけられているとか、救世観音の頭には釘が打たれているとか、怖い噂があるのです。
このような怖い話になったのは、梅原猛氏が書き下ろした「隠された十字架」という本が発刊され、古代史にユニークな着想で切り込まれた衝撃的な内容で法隆寺マニアを虜にした本なのです。
このような内容から「救世観音は怖い説」がうまれたのではないかと想定されます。
法隆寺の救世観音が怖いのか?そうでないのか?真実はただ一つ!
実際に見に行きましょう‼
目で感じて、心でどう感じたか?
それがあなたの答えになるかも知れません。
お寺や神社には、必ずと言っていいほど「祟り」や「呪い」などの伝説があげられます。
世界で最も古い木造建造物ならば、いろいろな伝説が浮上してもおかしくないかもしれません。
法隆寺の救世観音の公開【まとめ】
長年、完全秘仏とされてきた法隆寺の救世観音は、明治時代にフェノロサによってついに開扉されました。
その後、法隆寺の救世観音は春と秋に特別開扉されます。
修学旅行のシーズンや、これからも外国人観光客が増えることなどが予想されますので、救世観音公開のときは混雑も想定してお出かけください。
しかし、よ~く考えると、法隆寺の救世観音が700年間も誰も見たことがなかったのはやはり聖徳太子の呪いがかかっていると信じられてきたから?
皆さんはどのように思われますか?
最後までお付き合いいただきありがとうございました。