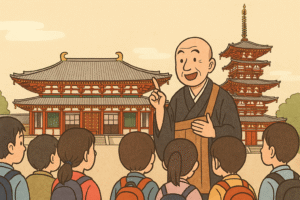薬師寺といえば、色鮮やかな三重塔や薬師三尊像が有名ですが、実はそれだけではありません。
1300年の歴史を感じさせる国宝や重要文化財が多く、建築・仏像・装飾の細部に至るまで見どころが満載です。
この記事では、薬師寺の有名なものを詳しく解説し、所要時間の目安も紹介します。
観光前の予習としてぜひご活用ください。
薬師寺の有名なもの!見どころと合わせてご紹介
三重塔(西塔)

薬師寺の三重塔は、日本で4番目の高さを誇り姿かたちも申し分ない美しい塔なのではないでしょうか?
薬師寺の三重塔は1981年(昭和56年)に再建されたばかりの、まだ新しい建物となりますが、高さ33.9m、お隣の東塔よりも30cmほど高いことが特徴です。
これは木材が縮むことがないように少し高めに設計され、200年後には東塔と同じ高さになることを想定して建てられたそうです。
次は薬師寺の三重塔の見どころといえば、やはり何といっても色鮮やかにそびえたつ姿が目を引きます。
昭和56年に再建されましたが、創建当初を思わせる姿なのではないでしょうか?
しかし時をかけるご都に、西塔も東塔のように古くなり高さも同じになっていくのでしょうね。
しかし、いつまでも絢爛豪華な建物であってほしいものです。
西塔の見どころとして、内部も必見です。
西塔の内部は、朱色に塗られた心柱を中心に四天柱があり、金色に輝く釈迦如来坐像が安置されています。
西院の四隅の軒先や垂木も見どころで、軒先には風鐸(ふうたく)という鈴形の飾りが取り付けられており、垂木の木口(こぐち)には金色の模様の入った飾り金具が取り付けられ、創建当初もこのように絢爛豪華に建っていたのだろうな…と感じながら拝観してみてください。
三重塔(東塔)

お隣の絢爛豪華な三重塔とは対照的にそびえたつ、もう1つの塔が東塔です。
見るからに古い建物で「あれ?なんで?」と思うかも知れません。
しかしこの東塔の三重塔こそ薬師寺の有名なものなのです!
それは、東塔は創建当時からの唯一の建物で、「凍れる音楽」とも称され、1300年間の歴史を誇る正に薬師寺の見どころも合わせ、必ずじっくりと拝観してほしい三重塔なのです。
東塔の見どころは、屋根にあります。
もちろん西塔も同じですので見比べてみてください。
一見、薬師寺の三重塔は6つの屋根がついているので、六重塔では?と感じる人も少なくありません。
しかし、よく見ると大きな屋根の下に小さな屋根があります。
この小さな屋根は、裳階(もこし)と呼ばれ、雨風を防ぐために付けられたとか。
また、薬師寺の法話の説明の中で、裳階のことを「スカートを履いている」という比喩的な表現をされていましたよ。
なるほどスカートとは、さすが薬師寺の法話は面白い発想をされますね。
他にも東塔見どころはまだまだあります!
東塔の相輪です!
何と東塔の3分の1を占めるそうで、相輪の先端部は重要な見どころとなります。
東塔の相輪の中の「擦管(さつかん)」は心柱を包む金属管ですが、一番下の擦管は天武天皇が皇后(後の持統天皇)の病気平癒を祈願して建てたと129文字で創建の経緯が刻まれていたそうです。
そして、「水煙」も重要な見どころで、高さ約2mの4枚の飾り板があり、火災から建物を守るためのもので、東塔の1番の見どころともいえるでしょう。
この水煙に24人の飛天が雲のなかで、花をまき、衣を翻し舞う姿、笛を吹く姿が透かし彫りされています。
1300年前にこのような発想があったことは、実に面白いと感じますし建築技術に関しても高度な技術が存在した事も「すごい‼」としかいいようがありません。
何より発想がとても豊かに感じました。
薬師寺の東塔は2009年から110年ぶりに修理が行われてきましたが、無事に修理を終え再び東塔の姿を拝観できるようになりました。
歴史の重さを感じる薬師寺の三重塔・東塔は西塔と共に、薬師寺のシンボルタワーとしていつまでも優美な建物であってほしいものです。
薬師三尊像と台座
📝#薬師寺 の本尊は薬師三尊像。国宝です。薬で人々を救うという薬師如来と、向かって右の日光菩薩が日勤、左の月光菩薩が夜勤の看護師役で24時間体制とか。
— 新美の巨人たち (@binokyojintachi) February 9, 2024
こうしたお話は薬師寺のお坊さんがとても楽しくお話してくださいます。修学旅行などで経験された方も多いのでは。#新美の巨人たち pic.twitter.com/EkR1saWfsm
薬師寺は健康祈願のお寺として有名ですが、健康祈願の願いを叶えてくださる仏さまがブロンズ像の薬師如来です。
薬師如来の両隣に立っておられる、左脇侍の日光菩薩、右脇侍の月光菩薩が安置されており三体合わせて、釈迦三尊像といいます。
薬師如来は字のごとく「薬」という文字から、私たちの健康を守ってくれる仏様です。
中央の薬師如来がドクターに例えると、日光菩薩は日勤のナース、月光菩薩は夜勤のナースを24時間体制で、皆さんの健康をお守りしていますと薬師寺の法話で聞いたことがあります。
日光と月光、つまり昼と夜ですね。
うまい!ナイス発想!
薬師寺の有名なもので欠かしてはいけないものが、薬師如来が座っておられる台座です。
この台座は、奈良時代から既に我が国日本はグローバル化されていたのでは?
と思わせる台座に薬師如来様はお座りになっていたのです。
薬師寺の見どころはこの台座で、何よりギリシャ・ペルシャ・インド・中国・日本のそれぞれの紋様が施され、この文様はシルクロードに沿ったものであることから、奈良時代は国際式豊かな国であったことが分かる大変貴重な台座になります。
この台座の見どころをもう少し詳しく解説すると、薬師如来が座る台座は「宣字形台座(せんじがただいざ)」とよばれ、框(かまち=建具の横の部分に入れる化粧台のこと)には、ギリシャの葡萄唐草文様、ペルシャの蓮華文様、中央の窓から裸形の力神が覗いており、下の框には、中国の四神とよばれる青龍・朱雀・白虎・玄武が施されているのです。
これらを辿るとシルクロードとして日本が国際的に文化を共有し、交易をしていたことがこれは薬師寺の見どころ間違いありません!
東院堂と聖観音菩薩立像|慈悲の心をあらわす国宝仏像

薬師寺の境内東側に位置する「東院堂(とういんどう)」は、奈良時代に建立された古い建物で、現在は国宝に指定されています。
薬師寺の中では静けさと気品を感じられる落ち着いた空間であり、訪れる人に深い感動を与える場所のひとつです。
《聖観音菩薩立像 しょうかんのん ぼさつ りゅうぞう》
— 日本美術史bot (@NihonBijutsushi) March 9, 2025
8世紀初・奈良時代
銅造・鍍金
奈良・薬師寺(東院堂所在)
撮影:小川晴暘(1894–1960)
出典:『小川晴暘と奈良飛鳥園のあゆみ』(飛鳥園・奈良県万葉文化振興財団編、2010) pic.twitter.com/LijpaC37uj
この東院堂には、「聖観音菩薩立像(しょうかんのんぼさつりゅうぞう)」という仏像が安置されています。
こちらも国宝に指定されており、薬師如来とは異なる穏やかな雰囲気をたたえた観音様です。
聖観音とは、悩める人々に寄り添い、救いの手を差し伸べる慈悲の仏とされており、東院堂の聖観音像はその優雅で穏やかな姿が高く評価されています。
高さ190cmほどの等身大で、スラリとしたプロポーション、滑らかな衣の流れ、そして慈愛に満ちた表情は、まさに「仏像の完成形」とも言われるほど。
特に注目したいのは、観音像の立ち姿です。
わずかに体をひねった「三曲法(さんきょくほう)」という技法が用いられており、見る角度によって雰囲気が微妙に変わる繊細な造形美が魅力です。
聖観音菩薩立像は、かつて聖武天皇の病気平癒を祈って造立されたとされ、東塔や薬師三尊像とはまた異なる歴史的背景も持っています。
厳かで、どこか母性すら感じさせるその姿は、心がすっと軽くなるような安らぎを与えてくれるでしょう。
薬師寺に訪れた際には、ぜひ東院堂にも足を運び、聖観音菩薩立像の前でゆっくりと時間を過ごしてみてください。観光客の少ない時間帯には、より静謐な雰囲気の中でその美しさを堪能できます。
大講堂|薬師寺最大の伽藍と仏教学問の中心

薬師寺の境内中央に位置する「大講堂(だいこうどう)」は、薬師寺で最も大きな建物で、東西約41m・南北約20mもの広さを誇ります。
元々は僧侶たちが仏教の教えを学ぶ場所であり、「講堂」という名前の通り、講義や学問の中心とされた重要な建築です。
内部には、弥勒如来坐像(国の重要文化財)を中心とした「弥勒三尊像」が安置されており、こちらも見どころのひとつ。
billboard classics
— みず玉 (@mizu_tama0913) April 28, 2019
玉置浩二✕西本智実イルミナートフィルオーケストラ
約1300年前にタイムスリップしたような2時間だった✨
薬師寺大講堂の弥勒三尊像を照らすライトが幻想的で、玉置浩二さんも感慨深かったと思う… pic.twitter.com/yVhCSRLnOF
薬師三尊像とは異なる柔和な表情が印象的で、未来仏である弥勒如来が人々を救済する存在として祀られています。
建築としても重厚感があり、堂々たる屋根の曲線や巨大な木造の柱は、訪れる人に迫力と静寂の両方を感じさせてくれます。薬師寺の中でも最も広い内部空間を持つ場所なので、ぜひ足を止めてゆっくりと鑑賞してみてください。
回廊と南門|一直線に伸びる軸線美と建築の美しさ

薬師寺の南側から境内に入ると、まっすぐ伸びた道の正面に南門(なんもん)、その奥に中門・大講堂が一直線に並んでいます。
この「一直線に並ぶ伽藍配置」は、薬師寺独自の美学ともいえるもので、視線をまっすぐ先に導く「軸線美」が非常に美しく、訪れた人の多くが思わずカメラを構えるスポットでもあります。

さらに、中門から左右に延びる「回廊(かいろう)」も見逃せません。この回廊は大講堂・金堂・東西の三重塔をぐるりと囲むように配置されており、伽藍全体を包み込むようなデザインが特徴です。
天平時代の建築様式を踏襲し、朱色と白のコントラストが非常に映える構造となっています。
建物そのものの美しさだけでなく、建築物が配置されている「空間」の美も薬師寺の魅力です。
南門からの眺めはまさに絶景ですので、最初に訪れる際はぜひその構図にも注目してみてください。
法話とお写経体験|心が落ち着く癒しのひととき
《はじめてのお写経》「お写経に興味はあるけど難しそう…」という方にオススメの入門講座「はじめてのお写経」を開催します。薬師寺の僧侶がわかりやすくお写経の作法や心構えをご説明します!
— 法相宗大本山 薬師寺 (@yakushiji_nara) June 5, 2025
日時:6月7日(土)10:30~
会場:お写経道場
志納料:3,000円
申込みはこちら!https://t.co/jrSK7Qs2G2… pic.twitter.com/Mj9FIoBl7q
薬師寺では、建物や仏像の拝観だけでなく、訪れた人の心を癒す体験も用意されています。
その代表が、法話とお写経です。
毎日行われている「法話(ほうわ)」は、薬師寺の僧侶によるお話で、仏教の教えをわかりやすく、時にはユーモアを交えて語ってくれます。
初心者でも入りやすく、「難しいお寺の話」という印象が大きく変わる体験になるでしょう。
観光で来た人も多く足を止め、思わず聴き入ってしまうほどの人気です。
また、お写経体験も人気のひとつ。
一文字一祈願という気持ちで筆を取り、静かな空間で心を落ち着けながら仏に向き合う時間は、他の観光地ではなかなか得られない特別な体験です。
完成した写経は奉納することも、自宅に持ち帰ることもできます。
観光だけでなく、心のメンテナンスとしてもおすすめの薬師寺。建物と体験の両面からその魅力を味わってみてください。
薬師寺の拝観にかかる所要時間は?
薬師寺で法話を聞いたり、お写経をしたりすると時間は大幅に違ってきます。
法話やお写経がある場合は2時間〜2時間半ほどが目安になるのではないでしょうか?
法話やお写経はなく、ゆっくりと参拝したい人の拝観所要時間は1時間〜1時間半が目安となるでしょう。
観光シーズンや法要などの参拝者が多いときは、時間をかけて参拝しても行列ができてなかなか思うように参拝できない可能性もありますので、予定していた時間より多くかかってしまったというケースもあるかも知れません。
あくまで、観光シーズンなど参拝者が多いときです。
今回ご紹介した見どころなどは、特に時間をかけてみてほしいと思います。
薬師寺の有名なものとは?【まとめ】
薬師寺の有名なものは、見た目の美しさだけでなく、1300年の歴史や国際文化との交流を感じさせるものばかりです。
三重塔や薬師三尊像、精巧な装飾が施された台座など、どれもじっくりと時間をかけて見たいものばかり。
薬師寺は「健康祈願」や「知的好奇心」の両方を満たしてくれる、魅力あふれるお寺です。
ぜひ現地でその奥深さを体感してみてください。